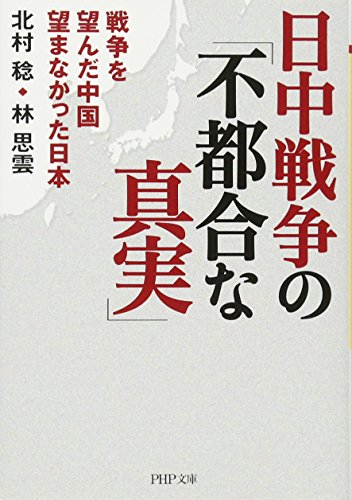盧溝橋事件が突発する少し前、1930年代半ばごろ。中華民国は世界各地に散らばった華僑の数を統計し、そのデータを発表している。
国民政府僑勢委員会たらいう組織が調査を主導したようだ。
それによると、
まず、タイに於いて二百五十万、
次いで英領マレーに二百二十万、
更に蘭印に百三十万、
仏印に於いて五十万、
それからビルマに二十万といった調子で、
その他諸々を合わせれば、だいたい七百万人弱というのが、当節南洋一帯に活動する華僑の総数だったらしい。
それで1937年。日中戦争の幕が上がるや、この七百万がいっせいに――少なくとも見かけの上では――、日貨排斥をやり出した。日本商品をボイコットして、日本の経済に打撃を与え、祖国を援助しようというのだ。
(Wikipediaより、盧溝橋一帯の航空写真)
むろん、ビルマの二十万とて例外ではない。その有り様を、山田秀蔵は一番近くで克明に眼に焼き付けた。
まず、ラングーンに日貨排斥華僑同盟などという、あまりにも直截な名前の組織が結成されたということだ。山田が初めてこの地を踏んだ明治三十七年の段階でさえ、ラングーンには五万人からの支那人が居て、既に堂々たるチャイナタウンを形成していたそうだから、ここを本部とするのはまったく自然の趨勢である。
なお、山田はこうした体験の積み重ねから――「ビルマを旅行するものは、どんな寒村僻地でも支那人の影を見ざるなきにおどろくであらう。(中略)ビルマの主要都市には何処にでも支那人街があって、支那商店が軒を列ねてゐる。雲南人は米屋、雑穀屋、宝石商を営み、福建人、広東人は多く大工職、家内工業、鉱山業に従事してゐる」――前述の数字を深く疑問視するもので、ビルマ華僑の実数は、下手をすると公式発表の倍近く、四十万に届くのではあるまいか、と指摘している。

あの国と地続きである以上、こういう現象はどうも不可避なようだった。
まあ、それはいい。
同盟の動きは目覚ましかった。ビルマ各地に点在している都合三百七十以上の華僑学校――ほぼ同時期、ナチスドイツは五十万の移民に対し、千三百の学校をブラジルの地に建てているから、比率の上では順当といっていいだろう――を足掛かりとし、またたく間に支部を展開。互いに連絡を緊密にして、愛国運動の実を挙ぐるべく、権謀術数を弄していった。
その具体的な遣り口を、山田は極めて詳細に書き残してくれている。
同盟の検察員といふものが、バッジをつけて支那人の店を歩きまわる。そして日本商品が置いてあったり、日本人が店先に立ってゐたりするのを見ると忽ち摘発する。それを新聞に載せて、何町の誰は日本人と交際してをった、向後華人は彼と交際してはならぬ、取引は停止しろと指令を出す。さうなると店は立行かなくなるから、しぶしぶ同盟の中に入り前非を悔ひて許して貰ふといふ風で、これは日貨排斥にかなり効果があった。(『ビルマ読本』51~52頁)
斯くの如きを眺めていると、漢民族に共産主義が馴染むわけだと心底納得したくなる。
相互監視、密告、私刑、吊し上げ――赤色国家に欠かせないこれらの要素は、なんのことはない、漢民族にとって第二の天性化してとうに久しきものであり、彼らを統御する上で、最も抵抗が少なく且つ有効な手段であった。
上に立つのが蒋介石だろうが毛沢東だろうが、やることに大して差異はない。なんといっても、「畑から兵士を取る」というスターリンの十八番を、蒋とて淫するほどに用いているのだ。

(ラングーンの電車)
雲南ビルマ間の貿易は生糸、綿糸、玩具、文房具など相当多数に上るが、実はすべて日本製品である。品物がビルマに入ってからレッテルを貼り替へて、さも支那製品か英米製品ででもあるかのやうにカモフラージュして売ってゐた。(52頁)
こういう体面さえ繕っておけばそれでいい、
ビルマには日貨排斥華僑同盟以外にも、商品不買委員会だの、空軍再建会だの、戦備者の友会ビルマ支部だの、数多くの華僑団体が立ち並び、構成員はみずからの愛国熱をアピールすべく、日夜励んでいたそうだ。
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。
この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。
↓ ↓ ↓

![]()