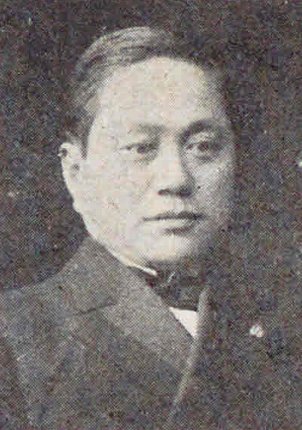吉田松陰に玉木文之進がいたように、伊藤博文には
松下村塾に入塾前の博文に、武士たるもののあるべき姿を文字通り叩き込んだ男である。
玉木文之進の教育態度が如何に苛烈なものだったかは、つとに世間に知られている通りである。講義中、蚊に刺された頬を松陰が掻くと、
「公に尽すべく学んでいる最中に、頬が痒いという私事を優先させるとはなにごとだ」
と色をなして叱りつけ、松陰を思い切りぶん殴ったというのは広く人口に膾炙された逸話であり、あまりにも有名なものだろう。私が過去にプレイした『テイルズオブベルセリア』の中にも明らかにコレをモデルにした、というよりそのものな描写が見て取れた。
来原良蔵も、決して玉木文之進に劣らない。
例えば草履だ。
来原は伊藤に暑季寒中のべつなく、この藁で編まれた日本の伝統的な履物の使用を厳禁し、素足のまま山野海岸を跋渉せしめた。その理由を語って曰く、
「もし戦地に在って草履を失い、しかも新たに得るあてもない状況に陥ったらどうするか。その時になって慌てても遅い。須らく平時より裸足での歩行に慣れておくに限る」
常在戦場とはこのことだろう。
当時の人々にとって、戦とはもはや何百年も前の面白おかしい風雲譚ではなくなっている。伊藤と来原が出逢ったのは安政四年、すなわち西暦1857年、幕府より毛利家に命ぜられた相州沿岸警備の最中、バラックの如き板小屋に起臥していた時分のこと。ペリーが浦賀に来航してから既に四年、桜田門外ノ変勃発まで僅か三年。攘夷の声が指数関数的な高まりを見せ、人心は確実に沸騰へ向かい熱を増す――これで戦争が起きない方がむしろおかしい、そんな土壌が出来つつあった。
自分がやっていることを、博文は別段滑稽とも思わなかったに違いない。
こんなこともあった。来原は冬の早朝午前四時、騎馬提灯を携えて博文の寝ている小屋へ行き、熟睡している博文を叩き起こして小脇に抱え、自分の小屋へ引っ張り込むと蝋燭の光を頼りに詩経書経の講義を始め、ついにはこれを毎日の習慣としたそうだから、おそらくはその一幕であったろう。冷え込みの特に厳しいある朝――粗末なバラックの小屋に防寒作用を期待するだけ愚かである――、つい博文は「寒し」と一言弱音を吐いた。
むろん、これを聞き逃す来原ではない。諄々と諭して曰く、
「寒いと言ったところで寒気の緩む道理がなかろう。ならば最初から寒いなどとは言わずにおくに如くはない。武士は何事もあくまで辛抱せざるべからず、愚痴と弱音は武士たるものの禁物なり、だ」
伊藤弥右衛門の株養子となる以前、取るに足らない豆粒のような童子の折から木の棒竹の切れを拾っては、それを振り回したり腰の帯に挟むなどして、
――俺は武士だぞ。
と昂然として鼻息荒く、ガキ大将を気取って憚らなかった博文である。
幼き日々の憧れは、依然彼の基底部、胸奥で、一向減衰することなくあかあかと燃え盛り続けていた。このため博文は、
――武士たるものは。
という言葉にひどく弱かったようである。
如何なる艱難辛苦だろうと、それを持ち出されるとようしやってやろうじゃねえか世間の凡百どもみていやがれと奮い立たずにはいられない。
或いはそんな可愛げこそ、ほとんど一目惚れに近い唐突さで、来原良蔵がいたく博文を気に入った根拠だったのではなかろうか。
力量と一致せざる自惚れは片腹痛いが、一致すれば壮観なのだ。
吉田松陰は玉木文之進あればこそ、わずか九歳にして明倫館の兵学師範に就任するという英才ぶりを発揮した。
伊藤博文も来原良蔵なくば、明治政府の大官たる後年の彼はあったかどうか。博文を松下村塾に導いたのも実質来原である以上、この表現は誇張でもなんでもない。
伊藤博文は後にこの師を回顧して、「豪胆にして実に克己心に富み、学識又深淵、真に文武両道の達人と称すべき人にして、その意思の強固なる、予は生来今日に至る迄、未だ嘗て彼の如きものを見たることなし」と述べている。べた褒めといっていい。あれほど厳しい、現代的な価値基準から観測すれば「教育」と云うよりほとんど「虐待」に近い躾を受けておきながら、その口吻には恨みがましいところが微塵もないのだ。
来原は、伊藤を真実武士として錬成したということだろう。
なお、この稿に挙げた逸話のほとんどは、明治四十三年刊行『藤公余影』なる書籍に依る。
伊藤博文の秘書官を長らく務めた古谷久綱という男が、ハルビン駅に於ける惨劇の後、慰霊と謝恩の意を込めて著したものだ。
国立国会図書館デジタルコレクション上に公開されて誰でも読める状況なため、興味のある方には是非一読をお勧めしておく。
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。
この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。
↓ ↓ ↓

![]()