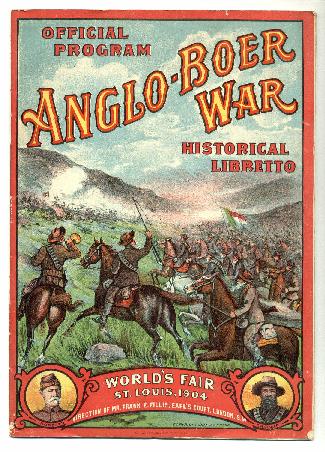ボーア戦争に先駆けて、ランズダウン卿が行った演説ほど世間を呆れさせたものはない。
イングランド中部、シェフィールドの地に於いて、彼はこう呼びかけたのだ。
「トランスヴァール共和国の失政の内、インド人に対する待遇以上に、余をして公憤を感ぜしむるものはない。哀れなるインド人たちが彼の地を追われ、母国へ引き揚げてゆくのを知りながら、英国がこれを看過して、南アフリカの一小国の不正をも矯正するの力なきことを暴露するとき、そのインド人に与える影響は、果たして如何なるものと諸君は思うか」
(Wikipediaより、トランスヴァール共和国の位置)
なるほど確かにトランスヴァール共和国――ボーア人が南アフリカにうち樹てた彼の国で、インド人たちは大変な不遇を
「トランスヴァールに於いて我らは土地を所有することを得ず、特定区域以外に居住することも許されず、ヨハネスブルグ及びプレトリアでは公然歩道を歩むことが出来ず、夜九時以降は外出することも出来ぬ。旅行には旅行免状を要し、汽車には一二等に乗ることが許されて居らぬ」
マハトマ・ガンジー、1896年10月26日、マドラスに於ける演説からの抜粋である。
トランスヴァールで弁護士業を営んでいた経験を持つガンジーだ。その言葉には一定の信頼を置いて構わない。
ボーア人たちは明らかに潔白ではないだろう。金鉱が発見されて以来、雪崩を打って押し寄せる外国人労働者により様々な問題が惹起され、国民感情をいたく傷付けたにしても、これは少々度が過ぎていた。
ランズダウン卿の言葉は正義と人道を重んじる文明国の紳士として模範的といっていい――彼らイギリス人がナタールで、ボーア人以上の苛烈さでインド人排斥に取り組んでさえいなかったなら。
――どの口がほざくか。
お前らだけには言われたくない、とトランスヴァール共和国は怒鳴り返してやりたかったろう。
なんとなれば、
土地財産の所有を禁じ、
入国時に登録税を課し、
居住は政府特定の区域に限るといえど、
兎にも角にもトランスヴァールはインド人の入国自体は認めているのだ。
それがイギリスはどうであろう。まさに同時期、ナタール法などという不気味な代物を設置して、
Ⅰ 官吏の要求により、ある種ヨーロッパの言語を以って移住願書を
Ⅱ 貧民、若しくは公費の負担となるべき虞れのある者
Ⅲ 白痴または瘋癲者
Ⅳ 悪性、若しくは危険性の流行病、若しくは伝染病を患える者
Ⅴ 到着前二年以内に、国事犯にあらざる罪を犯せる者
Ⅵ 醜業婦及び他人の醜業によりて生計を営む者
これらの条項に一つでも引っ掛かった輩を、ドシドシ門前払いにしているではないか。
更に言うなら、これで弾かれたインド人が、ならばとばかりに爪先を転じてトランスヴァールを目指すケースも数多い。
――いったいお前らに「公憤」を感ずる資格があるのか。
まともな神経の持ち主ならば、そう思って当然だ。
が、イギリス人にとって正気など、必要な時だけクローゼットから取り出して身に着ければいい、装飾品とさして変わらぬ存在らしい。1899年10月12日、彼らは平然と宣戦を布告、第二次ボーア戦争の幕が開いた。
背景が背景であるだけに、この戦いにはインド人たちも一方ならぬ貢献をした。前述のマハトマ・ガンジーも、2000人のインド人を糾合、衛生隊を組織して英軍のために尽力している。
戦前15000人のインド人がトランスヴァールに在ったのが、戦後の統計では12000人まで減少していたというから、流された血は決して些少の域でない。
そんな彼らに、勝利者たるイギリス人は何を以って報いたか?
むろん、ボーア人以上の弾圧である。
1903年には保安条例が制定され、インド人の入国を厳重に制限。その翌年には反インド人国民会議なるおどろおどろしい名前の組織がプレトリアで産声を上げ、議会はインド人排斥を公然と決議。裁判に関して、「被告がインド人である場合、判決には必ずしも証拠を要せず」と規定されたとんでもない修正案が可決したのは、1906年のことだった。
つまり待遇改善を期待して立ち上がったインド人は、それによって猶更ひどい窮境へ自らを追い込んだことになる。この摩訶不思議な現象は、
「インド人はパンを求めて石を投げつけられた」
と、当時の国際社会に於いて恰好の皮肉の材料となった。
が、当人たちにしてみれば、とても笑いごとでは済まされない。
――こんな馬鹿な話があるか。
怒髪天を衝かなければ、そいつはもう人間ではないだろう。
事実、人間としての尊厳が脅かされている事態である。イギリス人は必要な時だけ彼らを

(プレトリアの街と記念碑)
弊履に対してさえ、ここまで冷厳たる態度はとれまい。マキャベリズムの権化であろう。横紙破りの究極形、厚顔無恥とは彼らのために生れた言葉でなかろうか。
「かくの如き不可思議なる政府相手には、実に何事をも信頼する能わず」
カウニッツは正しかったと言わざるを得ない。然るにこれほど没義道を踏み、世界中から猜疑の目を向けられて――それでもなお、英国は生き延びている。
二度の世界大戦に於いても必ず勝者の席を占め、今日でもなお世界に対して一定の影響力を担保している。
真に瞠目すべきはこの事実こそだ。これは決して偶然ではない。イギリスを学べば学ぶほど、善因善果、悪因悪果など嘘っ八だと痛感される。
国際社会で生き残るために必要なのは畢竟権謀術数の手腕であって、情義も誠意も、それを構成する材料の一つに過ぎないのだろう。

(現在のヨハネスブルク)
トランスヴァールは1910年、南アフリカ連邦の一部として組み込まれた。
英国は当時に於ける最大規模の産金地――実に世界総額の半分に相当――を適切に運営、自国の地盤をますます鞏固ならしめたという。
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。
この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。
↓ ↓ ↓

![]()